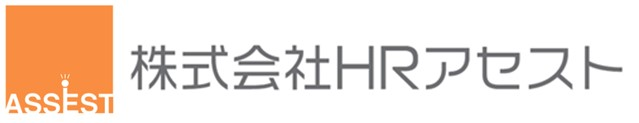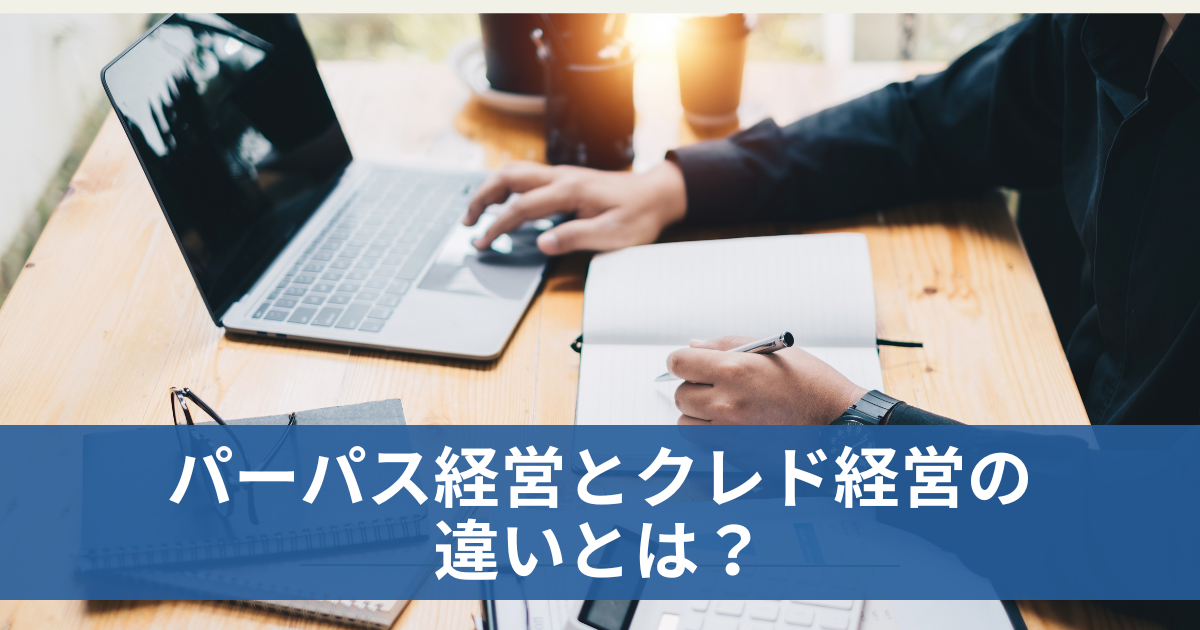はじめに
企業理念の重要性が叫ばれる中、経営者の間で「パーパス経営」と「クレド経営」という2つの言葉が注目を集めています。どちらも組織の理念や価値観に基づく経営手法ですが、その本質は大きく異なります。
これらを混同したまま導入を進めると、期待した効果が得られないばかりか、組織に混乱をもたらす可能性があります。経営者として、どちらを選択すべきか、あるいは両方を導入すべきか、悩ましい問題です。
この記事では、パーパス経営とクレド経営それぞれの特徴と違いを解説し、自社に適した選択肢を見つける手がかりを提供します。
パーパス経営の本質
パーパスの定義と意味
パーパスとは「存在意義」を意味します。企業経営におけるパーパスは、「なぜこの会社は存在するのか」「社会にどのような価値を提供するのか」という根本的な問いに対する答えです。
経営理念やビジョンと似ているように見えますが、パーパスはより本質的です。時代や環境が変化しても変わらない、企業存在の根幹を表現したものです。利益追求を超えた、社会的な存在意義を明確にすることが特徴です。
他の理念との違い
パーパスは、経営理念やビジョン、ミッションとは異なる特徴を持ちます。経営理念が「企業としての信条」を表現し、ビジョンが「目指す未来像」を示し、ミッションが「果たすべき使命」を表すのに対し、パーパスは「存在する理由」そのものを表現します。
例えば、経営理念が「顧客第一主義」といった価値観を示すのに対し、パーパスは「人々の生活を豊かにする」といった、より本質的な存在意義を示します。
経営への影響
パーパス経営は、意思決定の軸を明確にします。製品開発、事業展開、投資判断など、あらゆる経営判断をパーパスに照らして行うことで、一貫性のある経営が可能になります。
特に、事業ポートフォリオの見直しや新規事業の検討において、パーパスは重要な判断基準となります。パーパスに沿わない事業は、たとえ収益性が高くても、見直しの対象となります。
クレド経営の本質
クレドの定義と意味
クレドは「信条」を意味するラテン語です。企業経営におけるクレドは、組織の価値観や行動指針を具体的に示したものです。抽象的な理念を、日々の行動レベルまで落とし込んだものと言えます。
パーパスが「なぜ」を問うのに対し、クレドは「どのように」を示します。社員が判断に迷った時の道しるべとなる、具体的な指針を提供します。
行動指針としての役割
クレドは、日常業務における具体的な判断基準として機能します。顧客対応、業務遂行、社内コミュニケーションなど、様々な場面で参照される行動指針です。
抽象的な理念を「このような行動を取るべき」という具体的な形で示すことで、社員の自律的な判断を促します。マニュアルとは異なり、細かな手順ではなく、判断の基準を示すことが特徴です。
組織文化への影響
クレド経営は、強い組織文化の形成につながります。共通の行動指針を持つことで、部門や役職を超えた価値観の共有が進みます。
特に、社員の採用や育成において、クレドは重要な役割を果たします。求める人材像を明確にし、入社後の行動指針としても機能します。結果として、一貫した組織文化が醸成されます。
パーパス経営とクレド経営の7つの違い
目的の違い
パーパス経営は、企業の存在意義を社会的な文脈で明確にすることを目的とします。社会課題の解決や、人々の暮らしへの貢献など、より大きな視点での存在価値を追求します。
一方、クレド経営は、組織の価値観を行動レベルまで具体化することを目的とします。日々の業務における判断基準を示し、社員の自律的な行動を促進します。
表現方法の違い
パーパスは、抽象的で普遍的な表現を用います。時代や環境が変化しても変わらない本質を表現するため、簡潔で力強い言葉で表現されることが多いです。
クレドは、具体的で実践的な表現を用います。社員が理解しやすく、行動に移しやすい表現が重視されます。箇条書きや短い文章で、明確な行動指針を示します。
浸透プロセスの違い
パーパス経営では、対話を通じた理解の深化が重要です。経営層から一般社員まで、パーパスの意味を深く考え、議論する機会を設けます。時間をかけて浸透させていく特徴があります。
クレド経営では、具体的な行動への落とし込みが重視されます。研修や日々の業務を通じて、実践的な理解を促進します。比較的短期間での浸透を目指せます。
期待される効果の違い
パーパス経営の効果は、長期的かつ本質的です。企業の方向性を明確にし、社会との関係性を再定義することで、持続的な成長を実現します。イノベーションの源泉となることも期待されます。
クレド経営の効果は、より直接的です。組織文化の形成や業務品質の向上など、目に見える形で成果が現れます。顧客満足度の向上や社員のモチベーション向上にも効果があります。
評価指標の違い
パーパス経営の評価は、社会的なインパクトや長期的な企業価値など、広範な指標で行われます。株主、顧客、社員、地域社会など、様々なステークホルダーからの評価が重要です。
クレド経営の評価は、より具体的な指標で行われます。顧客満足度、社員満足度、業務品質など、数値化しやすい指標を用います。行動の変化を定量的に把握することが可能です。
社員への影響の違い
パーパス経営は、社員のキャリア観や価値観に影響を与えます。自社の存在意義を理解することで、仕事への意味づけが変わり、モチベーションの質的な変化が起こります。
クレド経営は、日々の行動や判断に直接的な影響を与えます。具体的な行動指針があることで、業務の質が向上し、自信を持って仕事に取り組めるようになります。
組織変革の方向性の違い
パーパス経営による変革は、価値創造の方向性を変えることから始まります。既存の事業や業務のあり方を、パーパスの視点から見直すことで、大きな変革につながります。
クレド経営による変革は、現場レベルの行動変容から始まります。日々の業務における判断や行動が変わることで、組織全体の変革につながっていきます。
パーパス経営に適した組織の特徴
企業規模による判断
パーパス経営は、規模を問わず導入可能です。ただし、大企業では部門間の調整や浸透に時間がかかる傾向があります。逆に、中小企業では経営者の想いを直接伝えやすく、浸透がスムーズです。
特に、従業員100人を超える企業では、パーパスを軸とした組織の一体感醸成が重要になります。事業や部門が多様化する中で、共通の存在意義を持つことが求められます。
業界特性による判断
社会的な影響力が大きい業界(医療、教育、環境関連など)では、パーパス経営との親和性が高いです。社会課題の解決に直接関わる業界では、存在意義を明確にすることが競争力につながります。
製造業やサービス業でも、社会的価値の創出を重視する企業では、パーパス経営が有効です。特に、BtoC企業では、消費者からの共感を得るためにも重要です。
組織文化による判断
社会貢献や価値創造を重視する組織文化がある場合、パーパス経営との相性が良いです。社員の自主性や創造性を重視する文化でも、パーパスは有効な指針となります。
一方、短期的な成果や効率性を重視する文化では、パーパス経営の導入に時間をかける必要があります。価値観の転換を伴うためです。
経営フェーズによる判断
成長期や転換期にある企業では、パーパス経営が効果的です。新規事業の展開や組織改革の指針として、パーパスが重要な役割を果たします。
特に、世代交代や事業承継の局面では、パーパスの再定義が求められます。企業の存在意義を改めて問い直すことで、新たな成長につながります。
クレド経営に適した組織の特徴
企業規模による判断
クレド経営は、中小企業での導入がしやすい傾向にあります。経営者の想いを具体的な行動指針として示しやすく、浸透度合いの確認も容易です。
従業員50人以上の企業では、部門ごとの特性を考慮したクレドの解釈や、浸透施策の工夫が必要になります。ただし、規模が大きくても、適切な推進体制があれば効果的な導入は可能です。
業界特性による判断
サービス業や小売業など、顧客接点が多い業界では、クレド経営が特に有効です。接客や対応の品質が重要な業界では、具体的な行動指針が必要不可欠です。
金融業や医療業など、高い倫理観が求められる業界でも、クレド経営は効果的です。判断基準を明確にすることで、適切な行動を促進できます。
組織文化による判断
規律や品質を重視する組織文化がある場合、クレド経営との相性が良いです。共通の行動指針を持つことで、さらなる品質向上が期待できます。
一方、個人の裁量や創造性を重視する文化では、クレドの表現方法に工夫が必要です。過度に細かい規定は避け、判断の基準となる指針を示すことが重要です。
経営フェーズによる判断
急成長期や組織改革期には、クレド経営の導入が有効です。新入社員の増加や組織の拡大に伴い、行動指針の明確化が必要になるためです。
安定期にある企業でも、組織文化の強化や業務品質の向上を目指す場合は、クレド経営の導入を検討する価値があります。
両者の併用アプローチ
効果的な組み合わせ方
パーパスとクレドは、補完的な関係にあります。パーパスで存在意義を示し、クレドでその実現に向けた行動指針を示す。この組み合わせにより、理念と実践の一貫性が生まれます。
具体的には、パーパスを頂点とし、クレドをその実現手段として位置づけます。クレドの各項目が、パーパスの実現にどうつながるのかを明確にすることで、社員の理解と実践が促進されます。
導入順序の考え方
一般的には、パーパスを先に定義し、その後クレドを策定する流れが自然です。パーパスで方向性を定め、それを実現するための具体的な行動指針としてクレドを作成します。
ただし、既にクレドを運用している企業では、パーパスの策定を機にクレドを見直すアプローチも有効です。クレドの内容をパーパスに沿って再整理することで、より強い一貫性が生まれます。
リソース配分の方法
両者の導入・運用には、適切なリソース配分が必要です。パーパスの策定と浸透には、経営層の時間と労力を重点的に投入します。対話や議論の機会を多く設けることが重要です。
一方、クレドの運用には、現場レベルでの継続的な取り組みが必要です。研修や日常的な実践支援など、運用面でのリソース確保が重要になります。
パーパス経営の導入ステップ
現状分析の方法
パーパス策定の前に、自社の強みや社会的な役割を分析します。創業の原点、これまでの歩み、社員の想い、顧客からの評価など、多角的な分析が必要です。
ステークホルダーへのヒアリングも重要です。社内外の声を広く集めることで、自社の存在意義に関する気づきが得られます。
策定プロセス
パーパスの策定は、経営層が中心となって進めます。社員からの意見も取り入れながら、企業の本質的な存在意義を言語化していきます。
外部の視点も取り入れることが有効です。顧客や取引先、場合によっては専門家の意見を参考にすることで、より普遍的なパーパスの策定が可能です。
浸透施策の設計
パーパスの浸透は、対話を重視します。経営層による説明会、部門ごとの討議会、一般社員を交えたワークショップなど、様々な対話の機会を設けます。
日常的な浸透策も重要です。社内報での発信、朝礼での共有、評価制度への反映など、継続的な取り組みを計画します。
クレド経営の導入ステップ
現状分析の方法
クレド策定の前に、現場の課題や価値観を把握します。部門ごとの業務特性、社員の行動傾向、顧客からのフィードバックなど、実践的な視点での分析が必要です。
既存の行動規範やマニュアルの内容も確認します。クレドとの整合性や、統合の可能性を検討します。
策定プロセス
クレドの策定は、現場の声を重視します。管理職や一般社員を巻き込んだワークショップを開催し、実践的な行動指針を検討します。
表現方法は、簡潔で覚えやすいものを心がけます。抽象的な表現は避け、具体的な行動に結びつく表現を選びます。
浸透施策の設計
クレドの浸透は、実践を重視します。研修プログラムの開発、日常業務での活用方法の検討、評価制度との連動など、具体的な施策を設計します。
部門ごとの特性に応じた浸透策も必要です。営業部門と管理部門では、クレドの解釈や実践方法が異なる場合があります。
導入時の注意点
経営者の役割
経営者は、パーパスとクレド、それぞれの本質的な違いを理解する必要があります。特に、パーパスを単なるスローガンとして扱わないよう注意が必要です。
経営者自身が体現者となることが重要です。決断や行動を通じて、パーパスやクレドの意味を示すことで、組織全体への浸透が加速します。
中間管理職の関与
中間管理職は、経営層と現場をつなぐ重要な存在です。パーパスの意味を深く理解し、部下に分かりやすく説明できる力が求められます。
クレドについては、日常業務での実践を促す役割を担います。部下の行動を観察し、適切なフィードバックを行うことで、クレドの定着を支援します。
社内コミュニケーション
導入の目的や期待される効果を丁寧に説明します。「なぜ今、パーパスやクレドが必要なのか」という点について、社員の理解を得ることが重要です。
一方的な押し付けは避け、対話を重視します。社員からの質問や意見に真摯に向き合い、双方向のコミュニケーションを心がけます。
モニタリング体制
パーパスとクレド、それぞれに適した評価指標を設定します。パーパスについては、社会的インパクトや長期的な企業価値など、広い視点での評価が必要です。
クレドについては、行動変容や業務品質など、より具体的な指標での評価が有効です。定期的なモニタリングを通じて、必要な改善を行います。
まとめ
パーパス経営とクレド経営は、異なる特徴と役割を持つ経営手法です。パーパスは企業の存在意義を示し、クレドは具体的な行動指針を提供します。
どちらを選択するか、あるいは両方を導入するかは、企業の状況や目指す方向性によって判断する必要があります。規模、業界、組織文化、経営フェーズなど、様々な要素を考慮することが重要です。
導入にあたっては、経営者の強いコミットメントと、段階的なアプローチが不可欠です。この記事で解説した違いや特徴を参考に、自社に最適な経営手法を選択し、組織の持続的な成長につなげてください。時代の変化が激しい今だからこそ、企業の軸となるパーパスやクレドの重要性は増しています。